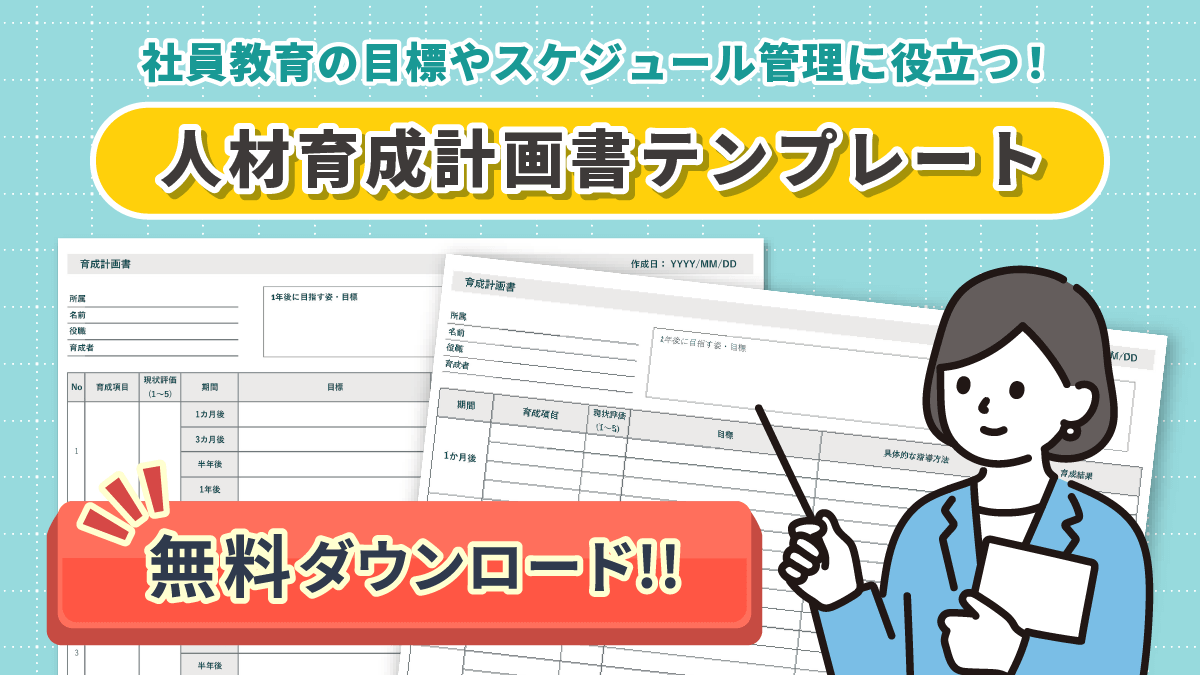社員教育を効果的に進める計画の立て方とは?
転職や独立へのハードルが低くなった今、企業では激しい人材の入れ替わりが起きています。それによって問題となるのが社員教育です。現に「社員の育成が間に合わない」「思うように社員教育を進められない」と悩んでいる方も多いことでしょう。
そこで本記事では、社員教育を計画的かつ効果的に行う方法について解説します。計画の立て方や計画例などの情報に加え、無料で利用できる計画書のテンプレートもご用意しましたので、ぜひご活用ください。
社員教育の計画はなぜ必要?
社員教育は、企業を存続させるため、企業が成長するために欠かせないものです。しかし、多くの企業が社員教育におけるさまざまな課題を抱えています。
.png?width=600&height=587&name=img_01%20(1).png)
「人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査(労働者調査)」(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)を参考に弊社で図を作成
例えば「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」が行った調査では、仕事をする能力を高めるうえでの課題として「従業員に必要な能力を、会社が考えていない」「従業員に必要な能力を、会社がわかりやすく明示してくれない」などといった回答が多く挙げられました。
これらの課題は、企業が社員教育の計画を立てていない、あるいは計画を提示・共有していないことが原因と考えられます。
自分自身にどのような教育が行われるのか、企業が行う教育の実態が掴めないと社員は不安に思うものです。それでは十分な成長は期待できないでしょう。
また「忙しすぎて、教育訓練を受ける時間がない」「十分な指導をしてくれる上司や先輩が身近にいない」といった課題も、無計画であることが原因と推測されます。計画を立てていないがゆえに、教育に必要な準備が整っておらず、時間や教育担当者を十分に確保できないのです。
このことから、社員教育を行う際は計画を立てる必要があるといえるでしょう。
社員教育の計画を立てる目的
実用性の高い社員教育計画を立てるためには、その目的を理解しておくことが大切です。何のために計画するのか、改めて確認しておきましょう。
社員教育を効率よく行うため
無計画に社員教育を行うと、指導のダブりやモレが発生する可能性が高いです。教育内容が重複したり、伝えるべき内容を伝え忘れてミスが発生したり……などといった問題が起こる恐れがあるのです。
社員計画は、そのような時間と労力の無駄を防止するために行います。教育の目的、内容、時期、手段など、予めプランを立てておくことで効率よく教育を遂行できます。
特に、近年は人手不足により、社員教育時間を十分に確保できない職場が多いです。限られた時間で社員を育てるためには、計画と準備がより重要だといえるでしょう。
必要な人材を確保するため
予測不能な時代といわれる現代。企業は、経済環境の変化に合わせて柔軟に適応することが求められています。
組織改革を実現するためには、人材の確保、つまり人材の育成が必須です。変化に間に合うよう、迅速に社員を育てるよう命じられるケースも少なくありません。
そのために用いられるのが教育計画です。いつまでに、どのような人材を確保する必要があるか、そのために何をすべきかを明確にすることで、効率よく社員を育成できます。問題が発生した際も、「計画」という軸があれば、すぐに軌道修正できるでしょう。
反対に、計画を立てずに取りかかると、育成が間に合わない可能性があります。必要な人材を確保し、企業戦略を着実に実現するためには、社員教育計画が必要不可欠なのです。
社員教育の方向性を示すため
「自分に必要な能力がわからない」「必要な能力を示してくれない」といった不満の声が挙がっていることから、従業員は自分の成長に対し不安を抱いていると推測できます。
社員教育計画および教育計画書は、そのような不安を解消するためのものでもあります。いつ何をどのような手段で学ぶのか、成長後どのような姿になるのかなど、ゴールとプロセスが見えることで、社員の不安が軽減されます。
また、教育の道筋を明確に示すことで、育成対象者・教育担当者・管理者など、関係者全員が同じ方向を向くことができます。共通のゴールを目指し、互いに助け合いながら人材育成に取り組めるのです。
モチベーションの向上、チームワーク力の向上は従業員の成長を促します。より効率良く社員教育の目標を達成できるでしょう。
社員教育の計画の立て方
社員教育を行う際は計画すべきとわかってはいるものの、何から始めれば良いか戸惑うこともあるでしょう。
そこでここからは、教育計画の立て方について解説していきます。
.png?width=600&height=338&name=img_02%20(1).png)
①目的の明確化
まず初めに、社員教育の目的を定めます。企業が求める人材の理想像、社員教育を行って成し遂げたい企業のミッションなど、何のために育成するのかを明確にします。
目的を明確化することで、教育の方向性が定まります。また、育成に必要な準備と期間も予想できるようになります。経営幹部や管理者と話し合いながらゴールを決めましょう。
②現状の把握
ゴールに向けて何をどれほど教えるべきか見極めるには、スタート地点を知る必要があります。そこで必要となるのが、現状の調査です。育成対象者のスキルの種類、スキルレベル、知識量などを把握することで教育内容が定まります。
現状を把握する方法の例としては「アセスメントサーベイ」が挙げられます。アセスメントサーベイとは、自己評価や、上司・同僚による評価に基づいてスキルを調査および可視化すること。効率化のため、外部のサービスを利用するケースが多いです。
その他、チェックテストを実施する方法もあります。現状を正確に把握するため、可能な限りスキル・知識のレベルを数値化するのがポイントです。
③必要なスキルの整理
ゴール達成に必要な知識・スキルを着実に習得するため、ここで情報の整理を行います。
例えば、一般職から管理職にステップアップするための社員教育を行う場合、コーチングスキルやティーチングスキル、ロジカルシンキングスキル、マネジメントスキル……と、さまざまなスキルを身につけなければなりません。
そこで、スキルに優先順位をつける必要があります。今すぐ習得すべきスキル、重点的に身につけるべきスキル、時間をかけて学ぶべきスキルと分類することで、適切なスケジュールを設定できます。
スキルの整理には「カッツ理論」というモデルや、「KPT」などのフレームワークなどが役立ちます。以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
■参考記事はこちら
人材育成計画とは?基本の立て方や計画書のテンプレート例を紹介
業務改善とは?目標の立て方やアイデア出しのためのフレームワークなど、効果的に進めるポイントを解説!
④目標設定
次に目標を設定します。知識・スキルを「どこまで」身につけることを目標とするのか決めます。
最終的なゴールは、目的の達成です。しかし、目標が大きすぎると従業員のモチベーションが下がる恐れがあるため、目標を複数の段階に分けるのです。育成対象者だけでなく、教育する側の従業員も、小さな目標を達成していくことで達成感が味わえます。
また、目標は育成期間中の指標にもなります。指標を目安に進捗を確認し、適宜問題の解決にあたることで、着実に最終ゴールへと近づけます。
社員教育の期限が既に決まっている場合は、スケジュールをもとに「いつまでに」「どこまで成長させたいか」目標を定めるのも良いでしょう。
⑤スケジュール設定
次に、いつ何を教えるのかなどの、細かいスケジュールを決めます。目標設定時にスケジュールが決まっていなかった場合は、この時点で「いつまでに目標を達成するか」を決めます。
多くの場合、社員教育の期限は経営戦略や人材戦略によって定められています。そこから逆算し、予め立てた目標をいつまでに達成するか、いつからいつまでに何を教えるか決めていくと良いでしょう。
決められた期間内に目的を達成できないことが判明した場合は、上層部との相談が必要です。全員が無理することなく、実現可能なスケジュールを設定することが大切です。
⑥教育手法の決定
次に、知識・スキルをどのように教えるか決めます。オンラインで行うかオフラインで行うか、複数の手法を組み合わせるかなど、具体的な手法を決めましょう。
どのような方法をとるにしても、少なからず準備が必要です。予め計画しておかないと、準備不足により、教育を実施できなくなる恐れがあります。シミュレーションを行い、どの手法が最も適切か、そのためにどのような準備が必要か考えましょう。
⑦社員教育計画書の作成
詳細が決まったら、いよいよ計画書を作成します。計画書の内容に決まりはないですが、例として以下のような項目を記載すると良いでしょう。
- 目的
- 目標
- 育成課題
- 対象者
- 教育担当者
- 教育手法
- 教育場所
- スケジュール
- 注意点 など
計画書を作成する際は、テンプレートを利用すると効率的です。弊社テンプレートを用意しましたので、計画書をわかりやすくスピーディーに作成したい方は、ぜひお役立てください。
【無料エクセルテンプレート】人材育成計画書
教育計画を立てる上でのポイント
社員教育計画、教育計画書は、計画・作成することがゴールではありません。あくまで効果的かつ効率的に社員を育成するためのツールです。
では、上手く活用するにはどのようなことを意識すれば良いのでしょうか。教育計画を立てる上での3つのポイントについて解説していきます。
ポイント1.教育方針やビジョンの明確化・浸透
社員教育には多くの人が携わります。全員が同じ方を向き、団結して取り組むには、一本の「軸」が必要です。
そのため社員教育計画を立てる際は、教育方針やビジョンを明確にし、全社に浸透させることが大切です。計画書に記載した上で、社員教育が「何を目指すのか」「何を果たすために行うのか」を説明しましょう。
方針・ビジョンが定まらないと、教育の進め方や教え方が関係者によって二転三転する恐れがあります。そのような状況は、教えられる側の従業員を混乱させてしまいます。誰の何を信じれば良いのかわからず、学習に集中できないでしょう。
よって、教育方針・ビジョンを示し、教育に一貫性を持たせることが重要なのです。
ポイント2.経営戦略・人材戦略との連動
社員教育は、企業戦略の実現に必要な人材を確保することが目的です。そのため教育計画は、経営戦略・人材戦略と連動させておく必要があります。
計画を立てる前に、予め経営戦略および人材戦略の擦り合わせを行いましょう。そして、戦略をもとに目標やスケジュールを設定することで、企業戦略に紐づいた教育計画を立てることができます。
教育計画の成功が人材戦略の実現につながり、それが経営戦略の実現につながる、という仕組みを作ることが大切です。
ポイント3.教育担当者など関係者との情報共有
社員教育に携わる関係者には、ビジョンだけでなく具体的な目標数値や教育手法、スケジュールなども共有しておく必要があります。特に、教育担当者や現場の管理者とは、細かい部分まで擦り合わせておくことが重要です。
なお、すべてが決まってから共有するのではなく、計画を立てる段階で話し合い、共に進めるのが理想的です。関係者を巻き込むことにより、疎外感によるモチベーションダウンを防げます。なかでも教育担当者の主体性・意欲性は、育成対象者の成長促進に関わるため、積極的に意見を取り入れながら進めたいところです。
情報共有には、教育計画書を活用できます。そのことを踏まえて、計画書は誰もが理解できるよう書くことが大切です。テンプレートを活用し、見やすくわかりやすい計画書作成を目指しましょう。
社員教育の主な手法
社員教育の手法は多岐に渡りますが、一般的なのは以下の5つの方法です。適切な手法を選ぶことで、効率よく従業員の成長を促せます。改めてそれぞれの特徴を確認しておきましょう。
.png?width=600&height=496&name=img_03%20(1).png)
①集合型研修(Off-JT)
集合型研修は、ひとつの場所に複数人の従業員を集めて行う研修のこと。大勢をいっぺんに教育できるというメリットがあります。また、ロールプレイやグループワークなど、受講者同士で交流しつつ学べる手法を実施できるのも利点です。
ただし、受講者の移動や宿泊にかかる費用・時間を負担する必要があります。また、受講者の職場が離れている場合、予定を合わせづらいというデメリットもあります。
教育計画を立てる際は、受講人数や教材の内容、実施する場所などの検討が必要になります。
②OJT(On the Job Training)
On the Job Training、通称OJTは、実践を通じて知識・スキルを身につける教育手法のこと。1人1人に合わせて指導できるのがメリットです。また、実用的なスキルを習得できる、疑問点や不安点をその場で解消できるなどのメリットもあります。
ですが、教育担当者によって教え方や教育の質がバラつきやすい点に注意が必要です。担当者と受講者のスケジュールが合わないと教育が滞る恐れもあるため、計画を立てる際は、スケジュールの調整が必要です。
③外部セミナーへの参加
外部企業が提供するセミナーに参加させる方法もあります。指定された場所に出向いて参加するオフラインのセミナーのほか、最近ではオンラインで完結するセミナーも開催されています。
外部セミナーでは、最新の知識や専門的な知識・スキルが学べるのがメリットです。また、自社の社員の負担が軽減されるため、多忙な企業や職場でも活用しやすいでしょう。
ただし、受講者以外は学習内容を把握できないため、教育計画時に予めアフターフォローを設計しておくことが大切です。
④オンライン研修
オンライン研修は、自社で実施する方法もあります。ビデオ通話をつないでオンラインで教育できるため、本社と受講者の現場が離れている場合や、時間の確保が難しい管理職者の育成にも有効です。
移動の時間や費用がかからないというメリットがありますが、グループワークやロールプレイを実施できないというデメリットもあります。また、その場での質疑応答が難しいため、受講者の疑問点を解消する工夫が必要です。
⑤eラーニング
eラーニングは、デジタルデバイスを使って知識・スキルを身につける教育手法のこと。動画視聴やスライド形式のコンテンツを利用するスタイルが一般的です。
受講者の都合の良いタイミングで、どこででも学べるのが最大のメリットです。予習・復習による学習効果の向上も期待できます。
ただし、コンテンツの作成にコストがかかる、システムの環境整備が必要になるといった課題もあります。教育計画を立てる際は、eラーニングを導入できる環境か、学習を管理するシステムがあるかなどの確認が必要と考えられるでしょう。
【階層別】社員教育の計画例
社員教育の計画を具体的にイメージするため、ここでいくつか例を挙げます。階層別にご紹介しますので、計画を立てる際は参考にしてみてください。
新入社員
新人教育は、入社したばかりの社員を一人前の社員へと育てることを目的として行われます。ビジネスマナーや業務に関する基礎知識など、基本的な知識・スキルの習得が求められます。また、ビジョンや企業方針、ルールなどを教育し、「自社の一員である」という意識を持たせることも新人教育の役割です。
さらに、早期離職を防止するため、上司や同僚との人間関係を構築できる環境づくりも大切です。集合研修、OJT、eラーニングを使い分け、これらの課題をカバーする新入社員計画を立てましょう。
|
教育・行動内容 |
教育手法 |
備考 |
|
|
入社後 1週間 |
・企業方針、ビジョン ・ビジネスマナー ・業務に関する基礎知識 ・コンプライアンスに関する知識 |
・集合研修(ロールプレイ、グループワークを含む) |
|
|
目標 |
企業方針・ビジョン、基本的な業務の知識を理解している |
||
|
入社後 1カ月 |
・実用的な業務の知識 ・状況別の行動指針 |
・OJT ・eラーニング |
eラーニングにて知識の理解度チェックを行う |
|
目標 |
業務に関する実用的な知識・スキルを習得している |
||
|
入社後 3カ月 |
・イレギュラー発生時の対応 ・これまでの知識、スキルの理解度を確認 |
・集合研修(グループワークを含む) ・OJT |
・集合研修にて振り返りを行う ・面談を行い、個々の疑問点/不安点を解消する |
|
目標 |
1人で業務を遂行できる |
||
中堅・若手社員
中堅・若手社員は、新人期間を終え、次のステップへと進み始める社員です。さらなるスキルアップのための知識・スキルの習得や、後輩指導スキルなどの習得が必要になります。
また、この頃からキャリアアップを見据えた教育も必要だと考えられます。面談やキャリア形成に関する研修を行い、将来に向けた準備を始めましょう。
|
教育・行動内容 |
教育手法 |
備考 |
|
|
4~5月 |
・キャリアデザイン研修 |
・集合研修 |
キャリア面談の実施 |
|
目標 |
自らのキャリアを描くことができる、今後のキャリアを管理者と共有し目標を設定している |
||
|
6~11月 |
・スキルアップ研修 ・コーチング、ティーチングスキル |
・集合研修 ・外部セミナー参加 ・eラーニング |
管理者による研修後のフォローアップ |
|
目標 |
次のキャリアに必要な知識・スキルが身についている、後輩指導ができる |
||
|
12月 |
・これまでの知識、スキルの理解度を確認 |
・集合研修 |
面談を行い、目標達成度や課題点を把握する |
|
目標 |
最終目標達成度90%以上 |
||
|
2~3月 |
・課題点を改善する知識やスキル |
・eラーニング ・オンライン研修/セミナー |
|
|
目標 |
最終目標達成度100%以上 |
||
管理職
部長や課長などの管理職には、高いスキルが求められます。教育内容のボリュームも大きく、期間も長くなりやすいです。
さらに、管理職者候補の社員は、既に多くの仕事を抱えている可能性があります。通常業務と育成を両立させるため、いかに効率よく教育を進められるかがカギとなるでしょう。
また、管理職に必要なマインドやマネジメントの知識などは事前に身につけられますが、実際に役職に就かないと経験できないことも数多くあります。OJTでの指導が難しいため、着任後のフォローアップ体制を予め計画しておくことが大切です。
|
教育・行動内容 |
教育手法 |
備考 |
|
|
第1フェーズ |
・マインドセット |
・集合研修 ・オンライン研修 |
|
|
目標 |
管理職者としての心構えを理解、意識している |
||
|
第2フェーズ |
・リーダーシップスキル ・マネジメントスキル ・ビジョン形成スキル など |
・集合研修 ・外部セミナー ・eラーニング |
管理者による研修後のフォローアップ |
|
目標 |
リーダーに必要な知識・スキルが身についている |
||
|
第3フェーズ |
・ロジカルシンキングスキル ・数値管理スキル など |
・外部セミナー ・オンライン研修 ・eラーニング |
・管理者による研修後のフォローアップ ・面談を行い、目標達成度と課題点を把握する |
|
目標 |
管理職者業務の遂行に必要なスキルが身についている、最終目標達成度90%以上 |
||
|
第4フェーズ |
・課題点を改善するためのブラッシュアップ |
・eラーニング ・オンライン研修/セミナー |
・面談による最終チェックを行う ・前任者による引継ぎ |
|
目標 |
最終目標達成度100%以上 |
||
|
着任後 |
・着任後に浮上した問題点の改善 |
・eラーニング ・オンライン研修 |
定期面談の実施 |
経営層
経営層候補の社員には、より幅広いスキルと豊富な知識、経験が求められます。教育する際は、幹部としての心構えなど、マインドセットから始める必要があるでしょう。
管理職の育成と同様、通常業務と両立させるための入念な計画が重要です。eラーニングやオンラインセミナーなど、場所や時間に縛られない教育手法を取り入れ、育成が滞ることのないよう配慮しましょう。
|
教育・行動内容 |
教育手法 |
備考 |
|
|
第1フェーズ |
・マインドセット |
・集合研修 |
経営者、現経営幹部による研修の実施 |
|
目標 |
経営幹部としての心構え・行動・言動を理解、意識している |
||
|
第2フェーズ |
・経営に関する基礎知識 ・意思決定スキル ・問題解決能力 |
・集合研修 ・外部セミナー ・eラーニング |
・アウトプットのための定期集合研修を行う ・面談の実施 |
|
目標 |
経営幹部に必要な基礎知識・スキルが身についている |
||
|
第3フェーズ |
・経営幹部の実務に必要な知識・スキル (経営戦略スキル、ビジョン形成スキル など) |
・集合研修 ・外部セミナー ・オンライン研修 ・eラーニング |
・アウトプットのための定期集合研修を行う ・面談の実施 |
|
目標 |
管理職者業務の遂行に必要なスキルが身についている、最終目標達成度90%以上 |
||
|
第4フェーズ |
・課題点を改善するためのブラッシュアップ ・経営戦略実行のための準備とフィードバック |
・eラーニング ・オンライン研修/セミナー |
|
|
目標 |
最終目標達成度100%以上 |
||
まとめ
社員教育は、一筋縄でいかないものです。計画を立てても、その通りに進まないことが多々あります。
それでも、より早く問題を解決し、迅速に軌道修正するには指針となる教育計画が必要です。研修や、その準備にかかる時間と労力を無駄にしないため、そして何より効果的に人材を育成するため、入念に計画を立ててから取り組みましょう。