OJT教育のメリットや成功させるポイントとは?教育担当の業務負担を軽減し、効率よく進める方法
昨今のサービス業界では、慢性的な人手不足が叫ばれています。人手不足となってしまう要因は離職率の高さといわれており、厚生労働省が調査した雇用動向の結果を見てみても、サービス業の離職率が群を抜いて高く、20%を超えている業種もあります。
離職による人手不足に備えるため、サービス業界、特に多店舗ビジネスでは常に従業員の採用募集をしています。学生アルバイトも貴重な人材であり、長く働いてもらうために手厚いフォローをしたいと思っていますが、現場ではそれができない現状があります。
本記事では、多店舗ビジネスにおけるOJTの現状と効率化のポイントについて、事例を交えてご紹介いたします。なお、本記事での多店舗ビジネスとは、飲食業や小売業など接客を伴うサービス業のことを指すものとします。
OJTとは
OJTとは「On The Job Training」の略称で、実際の業務を通して必要なスキルや知識を学ぶ方法のことをいいます。職場の上司や先輩が指導者となり、受講者は実際の業務に参加し手を動かしながら学んでいきます。
また、OJTは実務を通した指導方法であるため即戦力化が期待でき、一般的には新入社員や中途採用などの新人を対象として実施されます。
なお、OJT実施時の注意点などについては、下記の記事でもくわしく解説しておりますので、ぜひ参考にご覧ください。
■参考記事はこちら
多店舗ビジネスにおけるOJTの基本的な仕組み
全国各地に店舗を構える企業では、各店舗のアルバイト採用を本社が管轄せず、店舗の裁量に任せている所がほとんどです。
採用決定後は、雇用契約や時給についての説明を受け、業務に入ります。飲食店のホールであればオーダーの取り方、小売店であれば売り場の配置を覚えて在庫補充など、比較的簡単な業務から覚えていきます。マンツーマンで教えてもらい、流れが把握出来たら、教育担当者が側につきつつ一人で実践します。
言葉遣いや表情など、細かな部分のフィードバックを繰り返し、だいたい3か月程度で一連の業務が一人でもできるようになっていきます。
このように、多店舗ビジネスにおいては、従業員の採用から教育まで、各店舗の裁量に委ねられているのが現状です。これは店舗ごとの自由度が高いというメリットである反面、店舗ごとに教育の質やスキルの差がでやすいというデメリットともいえるでしょう。
OJT教育のメリット
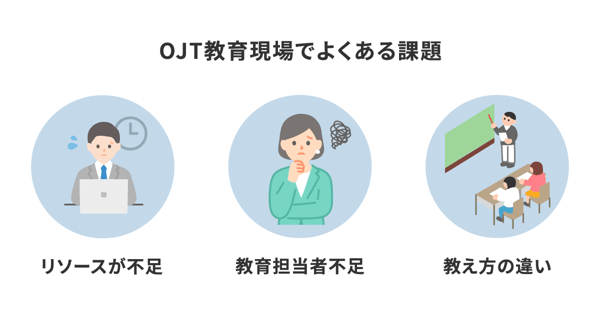
OJT教育には以下の4つのメリットがあります。くわしく見ていきましょう。
メリット1.個人に合わせた指導ができる
OJT教育の第一のメリットは、個人に合わせた指導ができる点です。
OJT教育は、基本的には教育担当者と受講者の1対1で行われるため、受講者個人のスキル習得度や性格、得意不得意などに合わせて指導方法を細かに変化させることができます。
そのため、たとえばすぐに身につけられたスキルについては時間をかけずに次の段階の指導をしたり、一方で苦手な業務については時間をかけて丁寧に指導をしたりと、柔軟な対応ができるでしょう。
このように、OJT教育は1対1だからこそ一人一人のペースに合わせた柔軟な指導ができるのが魅力です。
メリット2.経済的コストが低い
OJT教育の第二のメリットは、経済的コストが低い点です。
OJT教育では、教育担当者には上司や先輩など社内の人材を活用します。そのため、外部講師を招いて行うセミナーや集合研修などと比べて、教育にかかるコストを低く抑えることができます。
また、OJT教育では職場の既存の設備や資材を使用するため、特別な教材を用意する必要がありません。この点においても、教材の準備が前提となる集合研修と比べると大きなメリットといえます。
メリット3.教育担当者の成長も期待できる
OJT教育の第三のメリットは、教育担当者の成長も期待できる点です。
OJT教育を行うなかで、教育担当者は受講者に対して、業務をかみ砕いて説明したりモチベーションを上げる言葉のかけ方を工夫したりするため、コミュニケーション能力を向上させる機会を得ることができます。
また、新人を指導するなかでリーダーシップ力や人材育成力を養うこともできるでしょう。これは将来チームを率いたりプロジェクトを管理したり、マネジメント職に就くなどする際にも役立つ能力です。
さらに、OJT教育を進めるうえで自身の知識や経験を振り返って整理することや、時には自分が間違えて覚えていたことに気付くこともあるでしょう。正しい知識を再学習する機会としても、OJT教育が役に立ちます。
このように、OJT教育はマネジメント能力の向上や業務知識の再定着など、教育担当者の成長機会としても有効です。
メリット4.人間関係の構築が促進される
OJT教育の第四のメリットは、人間関係の構築が促進される点です。
まず、OJTでは1対1での教育が基本となるため、教育担当者と受講者間のコミュニケーションの機会が自然と増えます。これにより、お互いの信頼関係を築きやすい環境が生まるでしょう。
また、受講者側の観点では、分からないことがある時に質問する相手が明確であるため、安心感を持って教育を受けることが可能です。また、すぐに教えてくれる人がいることで、不安や孤立感を感じにくくもなるでしょう。
このように、OJT教育は教育担当者と受講者の信頼関係が築きやすいうえに、受講者にとっても心理的安全性の高い教育方法といえます。とくに、職場での人間関係構築が求められる新入社員に対しては、非常にメリットの多い教育方法といえるでしょう。
OJT教育のデメリット
上記のようにOJT教育には多くのメリットがありますが、一方でにデメリットもあります。
- 中長期的な指導計画が必要
- 教育担当者にかかる負担が大きい
OJTの実施期間は一般的に3ヶ月から1年と中長期的になるため、綿密な指導計画が必要です。しかし、人手不足の職場やOJT経験が少ない職場では効果的な指導計画を立てるのが難しい場合があり、効果的なOJTにつながらないことがあります。
また、OJTは基本的に受講者一人に対して教育担当者を一人配置し、手厚く指導を行っていくのが基本です。そのため、教育担当者は受講者の指導のために多くの時間と労力を割く必要があり、時として本来の業務に支障をきたすこともあります。
このように個人への負担が大きい点もOJT教育のデメリットです。
OJT教育現場でよくある課題
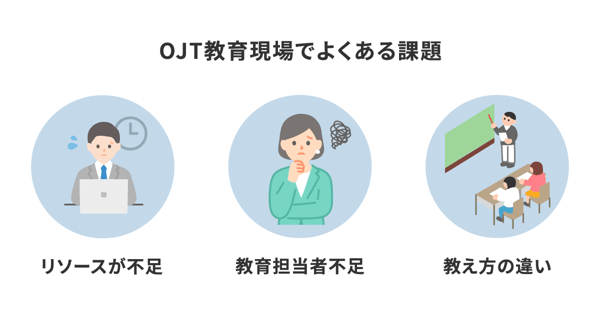 ここまでOJT教育のメリット・デメリットについて解説してきましたが、ここからはOJT教育現場でよくある課題とその解決方法について解説していきます。
ここまでOJT教育のメリット・デメリットについて解説してきましたが、ここからはOJT教育現場でよくある課題とその解決方法について解説していきます。
教育担当者のリソースが不足している
OJT教育現場でよくある課題の一つ目が、教育担当者のリソースが不足していることです。
教育担当者が他の業務に追われている場合、リソース不足により受講者に充分な教育時間を割くことは難しいものです。かろうじてOJTの形式を取っていても、受講者を丁寧に指導する時間も、フィードバックをする時間も確保するのは極めて困難でしょう。
またこのような場合、当然ながら効果的なOJTにはつながりにくく、受講者が充分にスキルを習得することは期待できません。
そしてこういった課題に対しては、外部講師や人材育成クラウドサービスの活用が一つの解決策となり得ます。外部ツールの活用方法については次の章でくわしく解説しますのでぜひご覧ください。
教育担当者の育成が間に合っていない
OJT教育現場でよくある課題の二つ目が、教育担当者の育成が間に合っていないということです。
教育担当者は誰でもできるものではなく、業務に習熟している人でなければなりません。そのため充分なノウハウを身につけている人材でなければ教育ができず、どうしても教育担当者となり得る人材は不足しがちです。
こういった課題に対しては、外部講師の招聘や自主学習での人材育成クラウドサービスの活用が一つの解決策となり得ます。これについては、次の章でくわしく解説しますのでぜひご覧ください。
教育担当者によって教え方が異なっている
OJT教育現場でよくある課題の三つ目が、教育担当者によって教え方が異なっているということです。この課題の主な原因としては、マニュアルの不備があげられます。とくに適切なマニュアル化ができておらず暗黙知(経験や勘で培ってきたスキルのように、言語や図で表しにくい知識)となっているノウハウは、教育担当者によって教え方が異なってしまう原因になりやすいものです。
また、教育担当者によって教え方が異なると、受講者が混乱する原因にもなってしまいます。特に多店舗経営の場合は店舗異動の際に業務手順が異なるなど問題になりやすいほか、サービス品質も一定に保つことが困難になるでしょう。
そしてこれらの課題を解決するには、業務のマニュアル化が必須です。くわしくは次の章で解説しますのでぜひご覧ください。
なお、暗黙知となっているスキルをマニュアル化する方法につきましては下記の記事でもくわしく解説しておりますので、ぜひ参考にご覧ください。
■参考記事はこちら
暗黙知と形式知の違いとは?変換方法やナレッジとしての活用についても解説
OJT教育を効率化するためのポイント
OJT教育現場でよくある課題を解決する方法として、ここからはOJT教育を効率化するためのポイントを解説していきます。よりくわしく見ていきましょう。
ポイント1.マニュアルを整備する
OJT教育を効率化するためのポイントの一つ目は、マニュアルを整備することです。新人が入るたびに同じ内容を教えているものに関しては、マニュアル化をすることがおすすめです。マニュアルを整備することで下記のようなメリットが得られます。
マニュアル整備のメリット
- 受講者が自主学習をできるようになるため、教育担当者の負担が軽減される
- 教育担当者ごとの指導のバラつきがなくなる
- 教育担当者が充分に育っていない場合でも教育を実施することができる
また、紙面でのマニュアルでは伝えるのが難しい技術的なノウハウに関しては、動画で作成するとわかりやすくマニュアル化することが可能です。
ポイント2.育成計画書を作成する
OJT教育を効率化するためのポイントの二つ目は、育成計画書を作成することです。一般的に3ヶ月から1年と中長期的な期間にわたって実施されるOJT教育は、どうしても途中で目的や目標を見失ってしまいがち。そのため、綿密な人材育成計画を立てることで教育の遠回りや無駄を防ぎ、効率的な指導につなげることが必要です。
その点、育成計画書を作成しておくことで、目指すべき場所を常に確認しながら進められるため、OJTがより効果的なものになるでしょう。また、目的とゴールに沿った無理のない教育計画を立てることで、OJTによる現場への負担を最小限に抑えることもできます。育成計画書を使って、上手にOJTを進めていきましょう。
とはいえ、育成計画書をゼロから作成するのはハードルが高いものと思います。そこで今回は、ゼロから作成した無料のエクセルテンプレートをご用意しました。下記リンクよりダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
なお、人材育成計画の立て方については下記の記事でもくわしく解説しておりますので、ぜひ参考にご覧ください。
■参考記事はこちら
人材育成計画とは?基本の立て方や計画書のテンプレート例を紹介
ポイント3.外部ツールを活用する
OJT教育を効率化するためのポイントの三つ目は、外部ツールを活用することです。
教育担当者のリソース不足や教育担当者の育成が間に合っていない場合、外部講師や人材育成クラウドツールなどの外部ツールを活用して教育を進めるというのも一つの手段です。
特に新卒採用時など新入社員が多数入社したような状況であれば、外部ツールを導入しても、一人あたりにかかるコストは抑えられます。無理にOJTを実施して現場に負担をかけるよりも、外部ツールの導入の方が会社にとってメリットが大きい場合も少なくないでしょう。
ポイント4.OFF-JTを併用する
OJT教育を効率化するためのポイントの四つ目は、OFF-JTの併用です。反転学習という学習方法をご存じでしょうか?反転学習とは、OJT実施前にあらかじめ自宅で知識をインプットしておき、その後OJTとして現場でアウトプットを行う学習方法です。
通常の学習方法では「アウトプット(学校で学ぶ)→インプット(自宅で宿題をする)」という流れが一般的ですが、反転学習では、その反対の「インプット→アウトプット」の流れにすることで高い学習効果が見込めるとされています。
さらには、企業による反転学習の活用はOJT教育の効率化だけでなく、下記のようなメリットも期待できると言われています。
反転学習を取り入れるメリット
- 個人の労働状況に応じた柔軟な学習ができる
- 理解度を確認しやすい
- 社員のスキル平準化に役立つ
- コミュニケーションを促せる
- 教える側のスキル・負担なく実施できる
なお、反転学習のメリットや実施方法については下記の記事でくわしく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。
■参考記事はこちら
反転授業とは?研修に導入するメリットや失敗しない実践方法について、事例からわかりやすく解説!
OJT教育の進め方
それでは実際にOJT教育を実施するにあたって、進め方を解説していきます。
まずは、OJT教育を実施するうえでの基本姿勢から見ていきます。みなさん、OJT教育と聞くと、教える側にスキルが求められるイメージがあるかもしれません。しかし実際は、「教える側」と「教わる側」の両方に求められるものがあります。
OJT教育を成功に導くためにも、これからご紹介する「教える側」と「教わる側」それぞれの心構えと取り組み方をぜひ参考にしてください。
教える側のすべきこと
OJT教育において、教える方がすべきことは相手に関心を持ち、相手の立場に立って考えることです。
「教える側」というとつい学校の先生のように一方的なコミュニケーションになってしまいがちですが、OJT教育での教える側は、双方向のコミュニケーションを意識することが欠かせません。
なぜなら、教わる側は自分とは異なるバックグラウンドや価値観を持っているため、ただ一方的に知識を伝えているだけでは、上手く納得できなかったり受け入れられなかったりすることもあるからです。
その上で、教える側のすべきことは大きく以下の3つに分けられます。
- 全体像と手順を「説明」する
- 「任せる」「説明する」を繰り返す
- 「気付かせ」「後押し」する
まずは、説明をして頭で理解してもらうことが大切です。そのうえで、説明だけでは伝わらない部分を実際にやらせてみる、そしてそれでも分からなければまた説明をします。一人でできるようになるまでフォローをしながら、自分で考え実行できるように後押しをしていきましょう。
教わる側のすべきこと
OJT教育において、教わる側のすべきことは教えてもらうことに対して感謝をし、謙虚な姿勢で学ぶことです。
教えてもらって当たり前とつい思ってしまいがちですが、感謝を忘れてしまっては信頼関係は築けません。また、こまめにメモを取ったり、わからないところはすぐに質問したりと学ぶ努力をし、勇気を持って挑戦することも大切です。
その上で、教わる側のすべきことは大きく以下の3つに分けられます。
- 頭で理解する
- 実践してみる
- 試行錯誤する
まずは説明を受けた内容を頭で理解するところから始めます。わからないところは質問するなどし、手順などを理解したら実践に移ります。実践をして「なぜできたのか」「なぜできなかったのか」を考えることも大切です。そして自立する頃には、自分で考え主体的に実施できるようにします。
OJTのやり方~4ステップ~
ここからは、より具体的なOJTのやり方について見ていきましょう。OJTのやり方は以下の4ステップに分かれます。
- やってみせる
- 説明する
- やらせてみる
- 評価・指導をする
まずは、教育担当者が実演して見せることで、受講者は業務の全体像を掴んだり、具体的にイメージできるようになります。
次に、ステップ1で見せた業務についてその業務の目的や意味を説明することで、その業務に対する理解を深めてもらいましょう。
続いて、実際にやらせてみる段階に入ります。実際に自分の手を動かしてもらうことで、「意外と難しい」「ここに注意しながらやるべきだ」などと新しい発見につながり、成長を促すことができます。
最後に、フィードバックを行います。先ほどの実践の結果をもとに、「どこが良かった(悪かった)のか」「なぜ良かった(悪かった)のか」「どう改善すればよいのか(具体的に)」を具体的に伝えましょう。なお、指導を行う上では、叱ることよりも「褒める」ことを意識することが大切です。
OJT教育の取り組み事例
それでは最後に、実際にOJT教育に取り組み、成功した事例をご紹介いたします。教育時間の削減に成功した事例、従業員のモチベーションアップやメンタルフォローに成功した事例、残業時間の削減に成功した事例の2パターンでご紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。
【事例1】OJT時間を50%削減!教育担当者不足の解消に成功(株式会社きちりホールディングス)
株式会社きちりホールディングスは、レストラン経営における飲食事業等を行う会社です。
この会社では、従業員数の増加につれて難しくなる人材育成に課題を感じていました。人材不足が加速する現場では、知識が人伝いの伝言ゲームになるなど間違った認識で理解が進んでしまう場面も多く、高いクオリティのサービス水準を浸透させることが難しくなっていたのです。
そこで、教育担当者不足を解消すべく、OJTに加えてOFF-JTも併用しようとクラウド型eラーニングサービスの『shouin+』を導入。2,000名を超える飲食店従業員に対して、動画ベースのマニュアルを整備しました。
すると、教育担当者不足が解消されたほか、統一された人材教育ができるようになったことでサービスのクオリティも保ちやすくなったといいます。また、サービス導入によりOJTにかける時間は50%も削減されたそうです。
実際に現場からは、「『なみなみスパークリングの注ぎ方』の動画を使ったパートナーの研修を行いました。動画を使うことで今まで勘違いしていた部分の修正も行え上手く注ぐことが出来るようになりました。動画を使うことで分かりやすくムラの無い研修を行うことができると感じました。」との声もあがっているそうです。
【事例2】研修を動画化、教育担当者の残業時間70%削減に成功(ココカラ本厚木店/人の森株式会社)
人の森株式会社は、フィットネスクラブ「フィットネス&スパ ココカラ」を展開する企業です。
この会社ではもとより、ジムトレーナーの人材育成に課題を抱えていました。1人のジムトレーナーを育成するのに約80時間を要しており、これが直接的に育成担当者の残業時間へとつながり大きな負担となっていたのです。
そこで、人の森株式会社では研修の効率化を目指し、クラウド型eラーニングサービスの『shouin+』を導入。トレーニングマシンの使い方やレッスンの進め方などを解説する研修内容を、動画マニュアルとして置き換えました。
すると、研修の一部がマニュアルに置き換わったことで研修の効率化を実現。育成担当者の残業時間は80時間から25時間まで減少し、55時間もの残業時間の削減に成功しました。また、育成担当者は「何度も同じことを説明しないといけない」というストレスからも解放され、メンタル面でも良い作用が働いているといいます。
まとめ
今回は、多店舗ビジネスにおけるOJTの現状と効率化のポイントについて、事例を交えながらご紹介いたしました。
多店舗ビジネスでは、店舗ごとに教育の質やスキルの差がでやすい一面があるため、効果的かつムラのないOJTを心がけていきましょう。
本文では、OJT教育の効果を高める4つの方法(①マニュアルを整備する②育成計画書を作成する③外部ツールを活用する④OFF-JTを併用する)について解説しましたが、人材育成を行う際はぜひこのポイントを意識しながら進めてみてください。




